最終更新日 2025年9月17日
.
◆大動脈弁輪拡大術(基部拡大術)が必要になるとき
.
大動脈弁狭窄症 などで 大動脈弁置換術(AVR) を行う際、弁の付け根(弁輪)が小さすぎて人工弁が入らない場合があります。
これを「狭小弁輪(small annulus)」と呼びます。
-
人工弁が十分なサイズで入らない → 狭窄が残る
-
最小サイズの人工弁すら入らない → 命に関わる
このような場合に、弁輪を拡大して適切なサイズの人工弁を入れる手術が 大動脈弁輪拡大術(大動脈基部拡大術) です。
.
◆代表的な大動脈弁輪拡大術の手法
.
1. ニック法(Nick法):もっとも基本的な方法 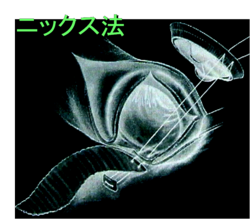
-
左冠尖と無冠尖の間を切り込み、弁輪を拡大
-
切り込み部分を 心膜パッチ で補填
-
比較的シンプルな手技で、人工弁を1サイズ大きくできる
※ただしパッチ縫合部の止血を完全に行う必要があります。
.
2. マノージャン法(Manougian法):さらに拡大したいとき 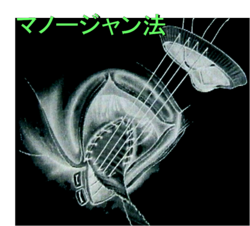
-
ニック法より深く、僧帽弁前尖まで切り込む
-
左房の天井も開き、複数のパッチで再建
-
技術的に難しく、止血操作も高度に必要
-
人工弁を2サイズ大きくできる
.
3. 今野法(Konno法):極端な狭小弁輪に
-
心室中隔まで切開し複数のパッチで再建
-
侵襲が大きいため頻度は少ないが、どうしても必要なときの選択肢
-
小児や再手術などで使われることがある
.
◆最新の拡大法:逆Y字拡大(Reverse Y-incision)
.
近年登場したのが スタンフォード大学 Bo Yang先生が開発した「逆Y字拡大」 です。
-
マノージャン法ほど深く切らないため 止血が容易
-
低侵襲でありながら3サイズ大きい人工弁が入る
-
将来的に TAVI(経カテーテル大動脈弁留置術)によるバルブ・イン・バルブ が可能となり、再手術リスクを大きく減らせる
例:70代女性で市販最小サイズ(19mm)の生体弁が入らないケース → 逆Y字拡大で21mm、場合によっては23mm弁まで挿入可能。
.
◆ なぜ大動脈弁輪拡大が大切か?
.
-
現代の人工弁は改良が進み、小さくても性能は上がっていますが、適切なサイズの弁を入れることが長期成績に直結 します。
-
特に 60歳以上で生体弁を希望する方 では、弁輪拡大ができれば 機械弁を避けられるケースが増える ため、妊娠・出産や生活の質(QOL)を考える上でも重要です。
.
◆ 実際の手術例
.
-
70代後半の女性:他院で「機械弁しか無理」と言われたが、当院で弁輪拡大を行い 生体弁の植え込みに成功。
-
このように弁輪拡大の技術があるかどうかで、選択肢や患者さんの人生設計が大きく変わります。
.
◆ まとめ:安全で確実な心臓手術のために
.
大動脈弁置換術(AVR)は比較的標準的な手術ですが、狭小弁輪に対応するには高度な技術が必要 です。
-
ニック法、マノージャン法、今野法
-
最新の逆Y字拡大術
.
これらを安全に使い分けられる 実績ある心臓外科チーム に任せることが、将来の再手術リスクを下げ、安心につながります。
.
お問い合わせはこちら

患者さんからのお便りのページへ
弁膜症のトップページにもどる
.
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。



