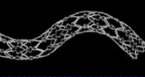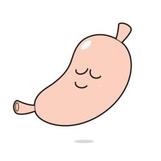SYNTAXトライアル(研究)5年のデータがでました。ライプチヒのモーアMohr先生らがとりまとめて権威あるランセットLancet誌から発表されました。
このSYNTAX研究では欧米の85施設で冠動脈の3枝病変か左主幹部LMT病変の患者さんを無作為にカテーテル治療(PCI)か冠動脈バイパス手術(CABG)に割り振り、その治療成績を年余にわたって比較検討したものです。
PCIでは第一世代のパクリタキセル徐放ステントを使用されています。
今回はその5年後の成績です。多くの循環器内科医や心臓外科医の注目のなかでの発表でした。
下のグラフで、赤い線がPCI後、青い線がCABG後の結果です。
1800名という大勢の患者さんを割り振り、897名がCABG、903名がPCI治療を受けましたた。
5年間で大きな心脳血管系事故(MACCE)発生はCABG後では26.9%でしたがPCI後では37.3%と多かったです(p<0.0001)(上のグラフをご参照ください)。
心筋梗塞になるのはCABG後は3.8%に留まりましたがPCI後は9.7%にもなりました(p<0.0001)。(これらも上のグラフを。)
血行再建繰り返しはCABG後は13.7%でしたがPCI後は25.9%と多かったです(p<0.0001) 。
がんその他、あらゆる原因を含めた死亡はCABG後が11.4%、PCI後は13.9%で有意差はありませんでした。
脳卒中も3.7%対2.4%で同様に差はありませんでした。
上のグラフでは両群に差がない項目は灰色で暗くしてあります。
冠動脈病変が軽い例(SYNTAXスコアが低い)でMACCEはCABG後28.6%に対してPCI後は32.1%と同レベルでした(P=0.43)。
LMT病変のあるCABG後では31%、PCI後は36.9%と差はありませんでした(P=0.12)。
しかし
冠動脈病変が中ぐらいある例(SYNTAXスコアがやや高い)では、MACCEがCABG後25.8%なのにPCI後は36%にもなり(P=0.008 )、
冠動脈病変が進んでしまったSYNTAX高スコアの患者さんにいたってはCABG後26.8%に対してPCI後44%とうんと高くなってしまいました(p<0.0001)。
冠動脈3枝病変の患者さんで比較検討したところ、CABGはPCIと比較して、MACCEも低く、死亡率や心筋梗塞でも大きく優れていました。
かつて脳卒中の予防ではPCIが有利と言われましたが、すでに差はないというレベルまでCABGは改善しています。
そこで結論は、、、
中または高度の病変がある(SYNTAXスコア中または高)ではCABGを今後も標準治療とすべきです。
低い病変(SYNTAXスコア低)やLMT病変(SYNTAXスコア中または低)ではPCIを行っても良い。
複雑な多肢病変がある患者さんにはすべて、心臓外科とインターベンション内科医の相談と最適治療への合意が必要です。
これまでの「PCIやれる限りやってよい」は否定されたわけです。患者さんの長生きや幸せにはならないからです。
このSYNTAXトライアルの結果は1年目からCABGが有利な傾向がありましたが、時間が経つにつれてその傾向が顕著になりました。
ディスカッションのなかで、PCIのステントはさらに新しく良いものが出ているから、今後PCIの結果はもっと良くなるとの意見もありましたが、ここまでの内容からは第二世代、第三世代の新型ステントも結果に大差なく、このSYNTAX5年の結果と同様のものになるでしょうとの見解がありました。
また日本とくに有力施設では体外循環を使わないオフポンプバイパス術が浸透しているため、CABGは一層有利になるでしょう。
時代は進んでいます。医学医療もそれに即応して、患者さんにベストなものを常に追求しなければならないのです。
患者さんにおかれましては、これから受ける狭心症治療の内容を内科と外科の両方から聴くという慎重な姿勢が安全安心のために望まれるでしょう。
虚血性心疾患のトップページにもどる
心臓手術のお問い合わせはこちらへ

患者さんからのお便りのページへ
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。