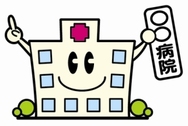胸部大動脈瘤はその部位によって心臓や脳、脊髄、腹部内蔵、などの重要臓器と関連するため、心臓血管手術の中でも昔から大きな手術として扱われて来ました。
近年は専門チームでの手術成績が格段に良くなり、病気の性質上、破れてしまうと手遅れになることが多いためもあって、やや早めに手術する方向にあります。
それだけに確実に、安全に治す必要があるとともに、今後破れる恐れの高い状態をより正確に把握し判断する努力も大切です。
日本循環器学会の胸部大動脈瘤における治療の適応ガイドラインはこうした意味でもお役に立つでしょう。以下、ガイドラインからの抜粋、要約です。
クラスI つまり強くお勧めできる治療法は
最大短径6cm以上に対する心臓血管手術
クラスIIa つまりお勧めできる治療法は
最大短径5-6cmで、痛みのある胸部・胸腹部大動脈瘤に対する心臓血管手術
最大短径5cm未満、症状なし、COPDなし、マルファン症候群を除く、の胸部あるいは胸腹部大動脈瘤に対する内科治療つまり点滴やお薬による治療
このように基本的に最大短径6cm以上か、それ以下でも症状があるときに手術となるわけです。
なおこのガイドラインには、マルファン症候群やのう状瘤を除く、と明記されています。
写真右は嚢状瘤の一例です。
マルファン症候群やのう状瘤つまりポコッと局所的に膨らむ瘤では6cmより小さい瘤でも破裂することが知られています。
そこでもう少し小さい段階でも心臓血管手術を行うことがあるわけです。
実際、直径5cmあまりの上行大動脈瘤をもつマルファン症候群の患者さんを定期健診していたところ、ある日突然A型解離を発生され、緊急手術でお助けした経験が昔、10年以上前にありました。
直径5cm程度でも解離が起こる恐れがあるため、もし強い胸痛発作がおこればすぐ病院へ来て下さいと平素から打ち合わせをしていたのが役立ちました。
その場合、当時の大学病院では緊急対応しづらいことも考え、近くの民間施設においでと伝えておいたのが功を奏し、ただちにその病院で合流し、緊急手術、軽快退院されました。
やはり備えあれば憂いなしですね。
またステントグラフト(EVAR)をもちいた治療も進化を続けています。
胸部大動脈瘤のなかでも下行大動脈瘤ではEVARは活躍の方向にあり、それ以外の弓部大動脈瘤などでもこれまでの手術が危険すぎるときなどに、弓部血管バイパス術と併用してEVARを行うこともあります。
今後が期待される領域でしょう。
これからもガイドラインをきちんと守って早め早めに対策を立てるのが良いでしょう。
血管手術や心臓手術のお問い合わせはこちらへどうぞ

患者さんからのお便りのページへ
真性胸部大動脈瘤のページにもどる
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。