最終更新日 2023年2月15日
1.まずバーロー症候群とは?
それは僧帽弁の弁尖つまりひらひら開閉する部分が大きく広がり過ぎて余り、モコモコと凹凸した弁のことです。弁尖が余っている状態とも言えます。
以下もう少しご説明します。
バーロー症候群(Barlow’s syndrome)は欧米にはよく見られる僧帽弁の病気で、人口の1-6%に発生するというデータもあり遺伝的要素のある疾患です。
故バーロー先生(右写真)初めて記載され、その名が残っています。
別名フロッピー弁症候群(floppy-valve syndrome、弱い弁という意味)とか膨らんだ僧帽弁症候群(Billowing mitral valve syndrome)などともいうように、弁が伸びて組織が瘤のように余ってしまい、きれいに閉じなくなった状態を指します。
左図の上がバーロー症候群の僧帽弁で前尖がもこもこと瘤化し変化していることがわかります。
左図の下が一般的な後尖逸脱のある僧帽弁で弁そのものの変化は軽いです。fibroelastic deficiency略してFEDとも呼ばれます。
著者は北米や豪州でこのバーロー症候群の手術を多数経験しましたが、近年は日本でも増えている印象があります(バーロー症候群の手術事例1)。
2.バーロー症候群の症状は?
症状は当初はあまりないことが多いのですが、弁の逆流が増えるにしたがって次第に動悸や倦怠感、めまい、息切れ、胸痛(狭心症とは違う形の)、偏頭痛などがあります。
バーロー症候群(Barlow’s syndrome)では弁尖がしばしば2つとも左房へ落ち込み弁の逆流(僧帽弁閉鎖不全症)が発生します。
その原因として考えられるのは、組織が変性し、弁尖が伸びてしまうことで、その組織変性は他の変性性の病気と関連していると考えられています。
バーロー症候群の患者さんの25%では関節の異常や高いアーチ状の口蓋、あるいは側彎やろうと胸、などの骨格の異常などが見られます。
3.バーロー症候群の診断と治療は
4.バーロー症候群の手術特に弁形成術は
手術では弁葉そのものが比較的柔らかいため、僧帽弁形成術が可能です。
ただし前尖・後尖含めた弁の大半を修復する必要がしばしばあり、熟練したチームでのみ形成可能です。
たとえば前尖の大半が逸脱していることも多く、しかもその前尖がしばしば瘤化しています。
そうなると前尖を適切に切除し、さらに人工腱索を多数立てて適切なかみ合わせを再現する必要があります。
私たちの経験では12本前後の人工腱索を前尖に立てればきれいにかみ合うようになります(手術事例4)。
さらに難しいのは、後尖も壊れていることが多く、そちらも三角切除や人工腱索などで再建する必要があります。
後尖の背丈が高すぎる場合はその高さを調整したり、取り付ける人工腱索の位置を調整してSAM(サム、後尖が前方へせり出し、それに押されて前尖が左室の出口を塞いでしまいます)をおこさないような工夫をします。
つまり前尖の人工腱索の長さ決定の通常の指標としている後尖の位置そのものがずれているため、前尖・後尖とも新たに造りなおすような工夫が求められるわけです。
人工腱索の4−6本も短時間で確実に立てられないチームではバーロー症候群の僧帽弁形成術が困難というのはそうした要求の多い手術だからです。
5.エキスパートが行う弁形成なら
患者さんの声はこちら
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。
お便り68 ポートアクセス法の僧帽弁形成術を受けたバーロー症候群患者さん
僧帽弁形成術は年々進化を続けています。
私たちも内外の仲間と常に切磋琢磨しながら、患者さんのお礼のことばを糧として、日々反省と勉強を続けています。おそらくこの仕事を続けるかぎり、その熱い毎日は止むことなく続くでしょう。
バーロー症候群はかつては弁形成がなかなか難しい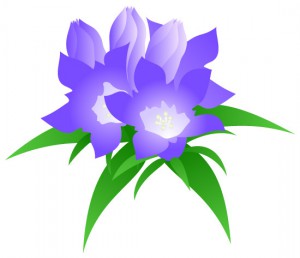 と言われました。現在でも慣れないチームには難問です。
と言われました。現在でも慣れないチームには難問です。
私たちもかつてはバーロー症候群で形成があと一歩のところで仕上がらず、涙を呑んで弁置換したことがありました。もう20年近く前のことですが、あの悔しさは今も忘れることができません。
そうした経験をもとに、いつしかバーロー症候群といえども、とくに問題なく普通に形成できるようになりました。
現在はこれをポートアクセス法という、ミックス手術のなかでも一番創の小さい、難しい視野の手術で普通にこなせるまでになりました。
そうすることで、より多くの患者さんが、より少ない痛みや苦しみで、より短期間に仕事復帰し、しかも心の傷がより小さくなって明るく人生の再出発ができるようになったことを、大変うれしく思っています。
以下はそうしたバーロー症候群の僧帽弁閉鎖不全症に対してポートアクセス法での複雑な僧帽弁形成術を受け、元気に退院された患者さんからのお便りです。
お役に立てて、こんなにうれしいことはありません。
*******患者さんからのお便り(心臓手術の体験記)******
米田正始先生
謹啓 9月になりましたが、まだ暑い日が続いています。
先生はじめ名古屋ハートセンターの皆様にはご清祥のことと存じます。
8月18日に退院し、長野県に戻りました。
手術に際しましては大変お世話になりました。
皆様優しい方ばかりで良い環境で入院生活を送ることができました。感謝申し上げます。
今振り返りますと、ここ2年ほど風邪がなかなか治らないような感じで調子の悪い時が何回かありました。
6月1日から36.9度~37.1度くらいの微熱が続き、たまに頭が痛い。
重いものを持ったり、5分も歩くと疲れてしまう。
自分の判断では、肝炎かもしれないと思いました。
かかりつけ医のところで血液尿検査を行いましたが、問題はない。
1ヶ月続いたところで総合病院に紹介していただき、7月6日(金)に診ていただきました。
内科の先生が聴診器を胸にあてて雑音を発見、心エコー検査して、すぐに循環器内科へ回されました。
「弁に逆流がある」「僧帽弁閉鎖不全症」「手術しないと治りません」「すぐに入院してください」私は、体の状態は理解できましたが、仕事のこともありすぐ入院といわれ焦りました。
「仕事の段取りを整えなければいけないので一度職場へ行かなければなりません」
「それじゃ、今日もう一度来てください。必ず来てください」 ‥‥ 16時再び参りました。
「月曜日入院してください」経食道エコーとカテーテル検査で2泊入院ということでした。
すぐ入院ではなかったのか。一度帰宅したときにインターネットで調べて職場には、本日入院、手術後3ヶ月療養と告げてきました。
時間をいただきましたので、土日インターネットで調べました。
闘病体験記がいくつもあり、写真を掲載しているものもありました。
スーパードクターを紹介するものもあり、低侵襲手術についても載っていました。
ポートアクセスのMICS手術は経験豊富な外科医が熟練したチームでおこなう。
どこの病院でもできるわけではない。
複数の病院がわかりました。
米田先生の「心臓血管外科WEB」「遠方の患者さんの場合は ‥‥ 自宅と病院の往復回数をできるだけ減らすよう、必要な検査等は集中的に行い ‥‥ 」とても姿勢が良い。患者思いの先生だと思いました。
「心臓血管外科WEB」に心カテーテル検査と経食道エコーは必要ないと書かれています。
私は検査を受けた方がよいのかメールで相談いたしました。
30分で返事が来ました。うける必要はないということでした。
米田先生の迅速な対応にビックリしました。
翌日、両方断っては申し訳ないと思い、経食道エコーだけは受けました。
担当の先生と話して、米田先生に手術をお願いしたいと考えていますと伝えました。
「じゃあ、紹介状書くから」と検査を受けないことを許してくれました。
帰宅後、名古屋ハートセンターへ電話し、米田先生の診察を予約しました。
担当の看護師さんに伝えてくださってあり、米田先生ってきめ細かいなあと感心しました。
夕方、手術日はいつか、職場復帰はいつ頃かメールでたずねました。
20分で返事が来てまたまたビックリしました。
7月18日名古屋ハートセンターで検査と米田先生の診察です。
手術日は8月7日と決まりました。
MICS手術でいける。
療養期間は8月いっぱい。9月から職場復帰。
CTも撮りました。
8月3日入院しました。
米田先生には、8月6日の手術が夜までかかり遅い時間にもかかわらず、私と家族に翌日の手術について1時間説明してくださいました。
私自身は、52歳でもう人生に悔いはないといつも悟ったような気持ちでいました。
加えて米田先生を信頼していましたので、手術に関して心配事はありませんでした。
「心臓血管外科WEB」で学習しているので、理解するというより確認するという感じです。
16日間入院し、僧帽弁形成術で治していただきました。
オペ室スタッフの皆様、北村先生、深谷先生、木村先生にもお世話になりました。
看護師さん、食事担当の皆様どうもありがとうございました。
清掃は行き届いていました。
担当の皆様ありがとうございました。
これで安心して残りの職業生活を続けられます。
1ヶ月後にはまた名古屋へ参ります。お世話になります。
20日には元の総合病院へ行ってきました。
担当の先生は、胸を見て、「ほう、右胸を切ったんだ。珍しい手術だね。内視鏡見ながらやるのかね。珍しいね。」とおっしゃるので、「見ていないのでわかりませんが、たぶんそうです」と答えました。
米田先生、お忙しいスケジュールと思います。無理をなさいませぬよう患者の一人としてお願い申し上げます。
また、名古屋ハートセンターがますます発展されますようお祈り申し上げます。
敬白
平成24年9月1日
****
*註:米田正始は現在、医誠会病院と仁泉会病院で仕事しています
患者さんからのお便りのトップページにもどる
心臓手術のお問い合わせはこちらへ
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。
バーロー症候群(Barlow’s syndrome)―形成できないというのは昔話? 【2025年最新版】
最終更新日 2025年9月13日
1.バーロー症候群とは?
.
バーロー症候群(Barlow’s syndrome)は、僧帽弁が過剰に伸びて「フロッピー弁(floppy valve)」のようになり、閉じが不完全となる病気です。欧米で多く報告されており、人口の1〜6%に発生するとされ、遺伝的要素が関与すると
考えられています。
別名として「フロッピー弁症候群」や「Billowing Mitral Valve Syndrome(膨らんだ僧帽弁症候群)」とも呼ばれます。
かつては「形成困難」と言われていましたが、現在は弁形成術の進歩により多くの症例で修復可能となっています。
.
2.主な症状と合併症
.
初期には自覚症状が乏しいこともありますが、逆流(僧帽弁閉鎖不全症)が進行すると以下の症状が見られます:
-
動悸、易疲労感、息切れ
-
胸痛(狭心症とは異なるタイプ)
-
めまい、偏頭痛
また、中等度以上になると以下のリスクが高まります:
-
心房細動
-
腱索断裂
-
心不全
-
突然死
-
感染性心内膜炎
.
3.診断方法と治療の基本
4.バーロー症候群の僧帽弁形成術
.
バーロー症候群では前尖・後尖ともに弁組織が余りやすく、複雑な形成術が必要です。
主な手術内容
-
前尖の切除・再建
-
**多数の人工腱索(必要なら12本まで)(手術事例4)**による強固な補強
-
後尖の三角切除や余剰弁尖切除・減高、人工腱索追加
-
SAM(収縮期僧帽弁前尖運動)を防ぐ工夫
このため、高度な技術と豊富な経験をもつ心臓外科医チームでなければ成功が難しいとされています。
.
5.専門チームによる治療で得られる安心と成果
.
経験豊富なエキスパートによる僧帽弁形成術では、長期予後は良好です。
-
弁輪にリングを装着 → 再発防止
-
腱索を人工腱索で強固に置換 → 弁の耐久性向上
-
前尖・後尖のバランス調整 → 逆流防止と心機能維持
さらに当院では、**小さな切開で行う低侵襲心臓手術(ミックス)**も導入し、患者さんの回復を早めています。また医学的にミックスが不適切と考えられる患者さんにはミックスではなくても術後の痛みの軽減をもたらす方法を用います
.
まとめ
バーロー症候群は「治せない病気」ではなく、エキスパートによる弁形成術で十分に改善可能な疾患です。
-
正しい診断と治療で生活の質を大きく改善できる
-
形成手術は人工弁よりも自然な心機能を維持できる
-
傷跡の小さいMICSや痛みの少ない正中アプローチも選択可能
「形成できない」と諦める必要はありません。
もし他院で「手術は無理」と言われた方も、ぜひ一度ご相談ください。
.
患者さんの声はこちら
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。



