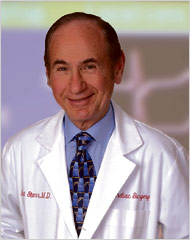この2月19日に第28回不整脈外科研究会(於、熊本)に参加しました。
日本心臓血管外科学会のサテライト研究会として毎年開催されている、不整脈外科についての実力派専門家の集まりです。今回は京都府立医科大学の夜久均教授が当番世話人でした。
数年前には私自身が当番で、充実したひとときを過ごさせて戴きました。
今回は「Maze手術後の心房機能について」、という渋いテーマでした。大変重要で患者さんにとって、大きな意味をもつものですが、意外に心臓外科医の世界ではあまり理解されていない領域でもあります。
はじめに代表世話人である日本医大の新田隆先生が心房細動手術における心機能というタイトルで講演されました。基調講演とも言える、内容のある、よくまとまった内容でした。
ついで不肖私、米田正始がMaze手術後の心房機能Update―心房縮小メイズ手術の検討からというタイトルで講演いたしました。
この10年ほど、メイズ手術でも治せない重症心房細動を心臓手術で治そうという意気込みで考案した「心房縮小メイズ手術」で、術後心房機能がけっこう回復することを示し、それゆえ、普通の心房細動の患者さんなら術後心房機能はもっと良くなるというメッセージを盛り込みました。
巨大左房と言えどもここまで小さくなり、これだけ動く、ということを実際の症例のエコーやMRIで示しました。かつてJTCVSやEJCTSから論文として世に問うた内容をリバイバル風にお示ししました。
さらに名古屋ハートセンターとかんさいハートセンターで行った101例の強化メイズ手術の検討から、心房機能が術後半年の間にかなり回復し、術後1年以後は除細動率・心房機能とも100%近いレベルに達することをお示ししました。
さすが超専門家の集まりで、さまざまなご質問を戴き勉強になりました。
1.心臓外科の大先輩である川副浩平先生の心房縮小手術とどうちがうのですか、
2.どういったラインで心房縮小するのですか
3.なぜこれだけ成績が良いのですか
などですね。
1.は、川副先生の術式が発表された時代はまだメイズ手術の概念が十分でなく、メイズ手術の切開線とは違う縫縮線を用いられたため、現代のメイズ手術→除細動へとはつながらなかった。私の術式はメイズ手術を考慮した縫縮線であるため、心房縮小と除細動を同時に達成できるという利点があることをお話ししました。
2.については、言葉でご説明するのは少々わかりづらいと考え、ちょっと違った形でお示ししました。つまり、Autotransplant(自家移植)の縫合線と同じラインを縫縮することをご説明しました。
3.は、左房が術後うんと小さくなること、MRI計測でなんと3分の1の容積になること、そして心房拡張の原因である僧帽弁閉鎖不全症が手術で解消されていることから術後には時間とともに心房が小さくなって行くこと、それが時間とともに除細動率が高くなっていくことにつながる旨をお話ししました。
弁形成のリングのためMRIのシグナルが乱れて計測が不正確になるのではないかという鋭いご質問を頂きましたが、幸い私は当時、デュランリングというもっとも柔らかい、金属がわずかしか入っていないリングを用いており、MRI画像への影響はほとんど問題なかったことをお答えしました。
その後のディスカッションの中でも、巨大左房が患者さんの長期生存率を下げるため、これを手術で解消することは患者にとって大変役立つことをご説明しました。
いろいろ御意見やご質問を戴き、感謝の発表になりました。
それから名古屋大学と京都府立医科大学から心房機能の検討の報告がなされました。
特別講演は愛知医大の磯部文隆先生の「Maze手術後の心房機能について」で、豊富な文献的考察と同先生の経験とがあわさり、学ぶところが多く、つい調子に乗っていろいろご質問させて戴きました。
あっという間に過ぎた2時間でしたが、これからの不整脈外科手術に役立つ情報が得られた充実したひとときでした。
新田先生、夜久先生、関係の皆様、ありがとうございました。東京医科歯科大学の荒井裕国先生、来年は当番世話人がんばって下さい。
ブログのトップページにもどる
心臓手術のお問い合わせはこちらへ
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。