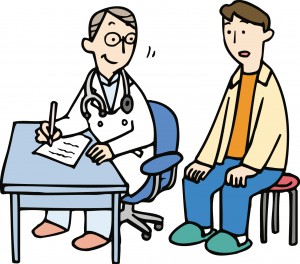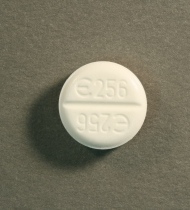恒例のハートバルブカンファランス(心臓弁膜症のユニークな研究会)が今年は大阪で行われました。当番世話人(会長)は大阪大学の中谷敏教授でした。
例年熱く楽しい、ときには厳しい議論に花が咲く研究会ですが、ことしは中谷先生のご尽力でいっそう盛り上がる内容となりました。参加者も年々増える中、記録となる300人に達しました。
オープンしてまだ新しいグランフロント大阪のナレッジキャピタルが会場で、便利でした。
まず大動脈弁狭窄症(略称 AS)の治療の最先端が論じられました。
東京慈恵会医科大学の橋本和弘先生が外科のAVR(大動脈弁置換術)の観点から、大阪大学の倉谷徹先生が低侵襲治療の観点からTAVI(カテーテルで埋め込む人工弁)の現況を講演されました。
私は自分の発表を前にしてパソコンが壊れたためその修理に忙殺され、部分的にしか聴けませんでしたが、倉谷先生の「日本人の大動脈基部の構造は欧米人とはちがう」というのが大変印象的でした。例えばバルサルバ洞が狭く、冠動脈入口部の弁輪からの距離が短いとなると、TAVIの際に冠動脈入口部をふさいでしまう恐れが増え、それへの対策がよりしっかりと求められます。欧米のEBM(証拠にもとづく医学医療、またそのデータ)は極めて重要かつ有用ですが、こうした人種差を考慮してベストの医療をこの国で行うことは極めて意義あることと思いました。
それからTAVIではPPMつまり患者さんのサイズや必要度に対して弁が小さすぎるという現象はあまりないという議論も面白いと思いました。軽い狭窄を残しても治療前より明らかに良ければ、患者さんにとって益する治療法ということになれば、より多くの患者さんのお役に立てるでしょう。
大阪大学の前田孝一先生と慶応大学の林田健太郎先生のエキスパートコメントも有用でした。前田先生が報告されたポンプ(人工心肺)下のTAVIは低心機能の患者さんでは有用で、これから心臓外科が循環器内科とハートチームで治療に当たるときにいざというときの切り札のひとつになると感じました。心臓外科と内科が普通のAVR、短時間で植え込める sutureless弁でのAVR、そしてオンポンプTAVI、最後にTAVIというラインナップの中で患者さんに一番適したものを選ぶ、これは治療成績が上がると思います。
林田先生は世界の現況も解説されました。ドイツではすでにTAVIを12万例もやっており、大動脈弁手術の43%を占める、これから二尖弁にもTAVIを検討する、血液透析も視野に入れるなどをお話しされました。TAVIの後もII度の大動脈弁閉鎖不全症を残すと予後が悪化つまり長く生きられなくなるため注意が必要です。
その他、サピエン弁は僧帽弁のバルブインバルブに使えること、コアバルブ弁は小さいサイズの生体弁へのバルブインバルブに適していること、冠動脈狭窄に対するOPCABとTransAortic TAVIつまり上行大動脈ごしにTAVIを入れる手術などもお話しされました。大変参考になりました。
ドイツなどではTAVIの出現後も外科のAVRは減ることなく、TAVIだけが増えるという現象が続いており、つまりTAVIは心臓手術を受けられない患者さんを助けるのに役立っていることを示され、これは以前からヨーロッパの報告で知ってはいたものの、現在も同じであることがわかり、興味深く拝聴しました。
引き続いて高度の左室機能不全つまり心不全にともなう中等度の機能性僧帽弁閉鎖不全症の治療のセッションがありました。
まず大阪大学循環器内科の坂田泰史教授が内科の立場から講演をされました。運動負荷試験とくに運動負荷エコーの有用性を示され、さらに左室の直径(Dd)65mm以上か左室収縮末期容積係数LVESVIが150cc以上が予後不良との中間解析結果を報告されました。私も比較的近いラインをこれまで発表しており、納得できました。さらに右室のDdや右房圧が予後に影響することを示され、これはいっそう同感しました。左心不全は補助人工心臓まで行かずともさまざまな工夫ができますが、右心不全の治療は打てる手がやや少なく、大きなブレイクスルーが必要と常々感じていたため、心強い仲間を得た感がありました。心拍数が心臓の予備力を反映するかも知れないという御意見も検討の価値があると思いました。
私・米田正始はこれまで進めてきた乳頭筋最適化手術(略称PHO)による僧帽弁形成術の最近の成績をご披露いたしました。
これまでこうした心機能の悪い患者さんへの僧帽弁形成術はあまり寿命を延ばさないという報告が多かったのですが、私たちの新しい術式(PHOによる僧帽弁形成術)では5年経っても心不全で死亡するひとが10%と、従来より成績が良いため今後さらに検討して行きたい旨をお話ししました。
このハートバルブカンファランスは症例検討中心の会ですので、心に残る一例をご披露しました。昨年末の日本冠疾患学会でも発表した症例で恐縮ですが、これがこのPHO手術の意義がいちばん判りやすいためご披露しました。
なにしろ、80歳近いご高齢で7年前に左室形成術(バチスタ手術と同タイプの手術です)と僧帽弁形成術を行った重症例でしたが、術後お元気でしたが7年後に大動脈弁閉鎖不全症を発症して僧帽弁閉鎖不全症を合併するに至り、危険な状態になって私のところに戻ってこられたのです。通常なら2弁置換をするか、1弁置換+薬治療で不完全治療で苦労するとことですが、私たちの方法で1弁手術の負担で3弁とも治し、わずか1日で集中治療室を退室されたのは、この手術の良さを示すものと思います。
川副浩平先生や新田隆先生、夜久均先生はじめ多数の方々から貴重なご質問やコメントをいただき、感謝するとともに充実感をもてたひとときでした。
ランチョンセミナーは聖マリアンナ医科大学の鈴木健吾先生の弁膜症における運動負荷エコーの重要性で、大変役立つ、面白い内容でした。鈴木先生は運動負荷エコーはこれまでのドブタミン負荷エコーと比べて血圧や心拍数の増加だけでなく全身の筋肉ポンプからの静脈還流増加も加わりより本物の、生理的な負荷であることを強調されました。運動負荷の終了基準の大切さや、運動で誘発される機能性僧帽弁閉鎖不全症の予後が悪いこと、CPXの有用性、とくにMRの量が15%を超えるといけないこと、大動脈弁膜症などでも手術前にこうして心臓の予備能を知っておくと役立つこと、運動負荷をかける時のエコーの画質の維持、などなど大変ためになりました。
午後のセッションは弁膜症症例を若手中堅の先生ががんばって苦労して乗り切ったケースを発表され、それに対してベテランが辛口の評価をするという面白いものでした。
聖路加国際病院の阿部恒平先生、慶応義塾大学の岡本一真先生、大阪大学の西宏之先生がそれぞれ含蓄ある弁形成手術症例を提示され、みどり病院の岡田行功先生、榊原記念病院の高梨秀一郎先生、さらに会場のベテランからさまざまな意見が寄せられました。こうした冷や汗症例を提示された若手中堅の先生方に敬意を表するとともに、皆で良いものを創るという方向のワークショップ的なディスカッションの場を企画された中谷先生に世話人のひとりとして御礼申し上げます。
最後のセッションでは同様の苦労症例を内科の立場から提示されました。川崎医科大学の林田晃寛先生、東京大学の大門雅夫先生、小倉記念病院の有田武史先生のいずれの症例も示唆に富むものでした。
女性の透析症例では圧回復現象が起こりやすくASの評価に注意を要すること、心房細動のときには先行RR間隔で計測値を補正する必要があること、PPM(人工弁のサイズが患者の必要に合わないこと)は生存率だけでなくQOLつまり生活の質も考慮すべきこと、巨大左房のAFで弁形成より弁置換すべきかどうか、高度のTRをどうするか、などなど有用な情報が山盛りでした。
なお巨大左房では私たちがこの10年間ちからを入れて来た心房縮小メイズ手術で除細動率が上がり、かつ左房内の血流がスムースになり血栓ができにくくなるため、この手術を取り入れれば今後の治療戦略も変わることを提案したかったのですが、その機会がありませんでした。
高度のTRつまり三尖弁閉鎖不全症では患者さんはたとえ生きておられても下肢が腫れ、体も動かしづらく、見ていて気の毒な状態の方が多いため、もっと積極的に手術を進めるべきであるという意見が多くありました。
世の中では、たかが三尖弁のために大きな創で手術するのは気が引ける、それと三尖弁置換術の長期成績が悪いため三尖弁形成術がやりづらいケースでは何もしない、などの考えが今も多くあると思います。そこで僭越ながら以下を意見させて戴きました。まず現代はポートアクセス法などで小さい創で三尖弁を治せること、そしてもし三尖弁形成術弁が不適である場合、生体弁で三尖弁置換術をやっておけば、将来TAVIでValve in Valveができることをお話ししました。
多くの活発な発表と討論で勉強になったカンファランスは無事お開きとなりました。懇親会でもまだ話が尽きないという印象でした。中谷先生、川副先生、世話人の先生方、ご苦労様でした。
来年度の当番世話人は誰になるのかと思っていたところ、代表世話人の川副浩平先生から私にご指名があり、来年度の当番をさせていただくことになりました。
これまでの同様、あるいはそれ以上に皆さんが楽しめる、勉強できる、普通の学会とは少しちがう良さのある会にしたく存じます。皆さんよろしくお願い申し上げます。
平成26年3月10日
米田正始 拝
心臓手術のお問い合わせはこちらへ
ブログのトップページにもどる
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。