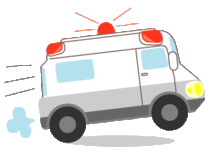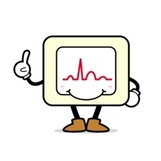成人先天性心疾患は生まれつきの心臓病が大人や場合によっては高齢になってから悪化するものも含まれます。
修正大血管転位症もその一つで、心臓の中に穴があいておらず、狭いところなどもなければ、若い間はまずまず元気に暮らせます。
しかし年齢とともに新たな病気や問題が発生し、次第にそれらが命取りになることがあります。
修正大血管転位症(強い左室と弱い右室が入れ替わっており徐々に無理がかかる)の場合は
三尖弁閉鎖不全症(普通の状態なら僧帽弁閉鎖不全症に相応)が発生すると心臓の力が落ちて行きます。
患者さんは70歳女性で
修正大血管転位症と三尖弁閉鎖不全症そして僧帽弁閉鎖不全症のためどうしても心不全が取れず岐阜県から来院されました。
しかも心臓の位置が通常と左右反対になっており(右胸心といいます)、手術の際にはさまざまな工夫が必要な状況でした。
無事手術はでき三尖弁は人工弁(生体弁)で、僧帽弁は弁形成できれいになりました。
弱った心臓のパワーアップを図るよう、三尖弁の乳頭筋も温存し、心房の「キック」(ちょっと専門的ですみません)も効くように工夫しました。
すっかりお元気になられ、お手紙を頂きました。
お手紙を拝見し、派手ではなくても、素晴らしい人生を歩んでこられたこと、
そしてその素晴らしい人生に心臓手術によってお手伝いができたことをひとりの臨床医・外科医として誇らしく思いました。
この弱った心臓で農業をこなし、命を賭けて子供さんを産み、頑張り続けられ、
しかし一時間でもいいから楽な呼吸がしてみたい、、、
こういった患者さんをお助けするため自分は長年心臓外科の修業と研究を積んで来たのだとお手紙を読んで改めて思いました。
私の方こそ感動を頂いたように思えます。
***************患者さんからのお便り***********
米田正始先生
その後いかがお過ごしでしょうか。
手術の節には本当にありがとうございました。
修正大血管転位症 右胸心と言う病気を持って生まれて七十年の歳月を歩んで来て、
でも元気いっぱいと言うわけにはいかず、苦しい時間の方が多い日々でした。
年齢と共に体力も心臓も弱ってきて、
農家に嫁いだ私には仕事は重労働でとても辛いものでした。
そして子供を生むことは無理だと言われましたが、それでも子供は欲しく、
命懸けで二人の子供を授かることができ、今ではとても有難く幸せに思っています。
心臓の調子がだんだん悪くなり、六十歳頃手術を勧められましたが、
その頃には手術をする気持ちにはとてもなれませんでした。
でも時々起こる発作に苦しみこのまま心臓が止まってしまうのではないかと恐怖心を感じた事も何度かありました。
一度飲むだけでも何種類とたくさんの薬をもらい、飲み続けてどうにか普通の生活も出来ておりましたが、
七十歳になった頃から急激に心臓の衰えが増してきて体力もなくなり、
手足は夏でも冷たく、顔や足など浮腫んで横になっている日が多くなり、
話をするにも息切れがし、声を出す力も弱くなってしまいました。
お世話になっている病院の先生も弱っていく私の体を心配して下さいましたが、
私自身、気力も体力もなくなっていくばかりで残りの寿命も終わりが近づいている気がしてとても悲しい思いが込み上げてきました。
でも終わりになる前に一日でも一時間でもいいから健康な人と同じ様な呼吸がしてみたいと切実に思いました。
そんな苦しみの中で、ある日明るい希望が見えてきたのです。
その希望というのはハートセンターという病院です。
心臓専門で優れた経験と腕を持った米田先生を紹介して頂き、
兎に角一度お逢いして診ていただこうと車で二時間余りかけて米田先生を訪ねました。
体の疲れ、不安、心配をしながら米田先生にお逢い出来、早速色々な検査をして頂き、
検査の結果を丁寧に説明して下さり聞いているうちに想像以上に悪くなっている自分の心臓に驚いて、又、不安になってしまい、
それでも先生の「手術をすれば元気になれる」という言葉を聞いて安心はしたものの、
大変な事には間違いなく、すぐには決心は出来ません。
家に帰ってからも毎日色んな事を考え悩み、しばらくして二度目の診察日がきても気持ちは迷うばかり。
家族も手術を勧めてくれるし思い切って手術を受ける心を決めました。
体の方は苦しくなるばかりだし三回目の診察の日に入院させて頂き、
手術に向け体力を作る治療が始まりました。
四月二十日に手術を受けました。
怖いのと心配でいっぱいでしたが、もしこのまま目が覚めなくても寿命だと思い・・・
どの位の時間眠っていたのかわかりませんが、先生に声をかけられパッと目覚めた時、
「あっ生きている」と感じ、病室の明かりが本当にまぶしく目の中に入ってきたことを思い出します。
意識が朦朧としている中、喉の乾きがひどく水が欲しいと無理を言った事も覚えています。
時間が経つにつれ、あんなに苦しかった心臓がとても楽になっている事に気が付き、
これって本当かしらとすぐには信じられませんでした。
呼吸をしているのが不思議に思えました。
うれしい、良かった、生きていて良かったと涙があふれました。
米田先生はじめ北村先生、深谷先生、優しい看護師さん、
そして私に携わって下さった大勢の方々のお陰様で絶望から希望に変わり、
夢のような思いで毎日を送っています。
手術の日から十二日目には早くも退院ができ、
一日一日と元気になっていく私を家族も驚くほどです。
十月二十日で半年が過ぎ、経過を診てもらいに行き、笑顔で先生とお話でき、本当に良かったと思います。
まだまだ元気になれると言われ、益々元気が出てきました。
苦しい日が続くとどうして私ばかりがこんなに不幸な人生かと他人を羨み、生んでくれた親をつい恨んだりもした事が、
今は生まれて来て良かったとこんな大きな喜びを感じられる私は幸せ者だと思える様になりました。
私の命を救って下さった米田先生には感謝の気持ちでいっぱいです。
うまく言葉に表す事が出来ない私ですが、救われた命を日々大切に一生懸命生きていきたいと思います。
現代の医学と米田先生を信じて受けた手術はすごいものでした。
苦しんだ後の幸せはとても大きいものです。
本当に本当にありがとうございました。
平成21年11月**日 ****
患者さんからのお便り・メールへもどる
心臓手術のお問い合わせはこちらへ
執筆:米田 正始
福田総合病院心臓センター長
医学博士 心臓血管外科専門医 心臓血管外科指導医
元・京都大学医学部教授
----------------------------------------------------------------------
当サイトはリンクフリーです。ご自由にお張り下さい。